コラム
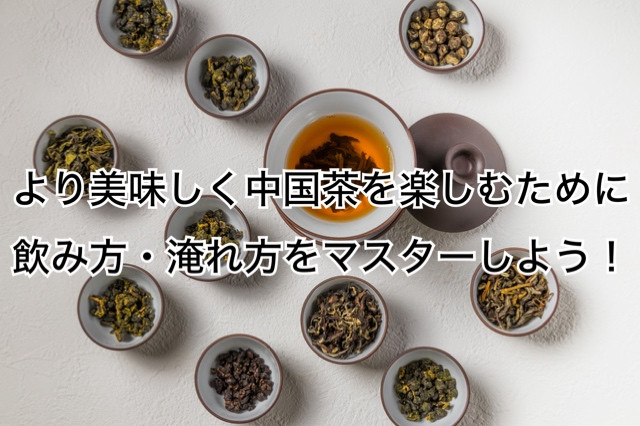
中国茶には何通りもの淹れ方があります。
しかし、これでなくてはいけない、という日本の茶道のようなルールはないので、気軽に考えていただけたらと思います。
先ずは、お茶を飲む前に深呼吸を3回
一煎目は、香りを楽しむ
二煎目は、味を楽しむ
三煎目は、余韻を楽しむ
おいしい淹れ方を覚えたら、もっともっと中国茶の楽しみが広がりますよ。
『さまざまな淹れ方を覚える』
中国茶に少しでも興味のある人なら、茶童(急須)に湯を溢れるほどに入れたり、茶童の上から湯をかけたりする淹れ方を見たことをある方もいるのではないのでしょうか?
これは「工夫(功夫)茶」といわれるもので、丁寧に淹れるお茶のことを意味しています。
しかし、中国茶の淹れ方はこれだけではありません。それぞれの茶葉が個々の特徴をもつ中国茶には、その茶葉の特徴に合った茶器や淹れ方があるのです。
『茶葉に合った茶器を選ぶ』
味だけでなく、香りや茶葉の美しさを楽しむことが重要な中国茶では、茶器選びもポイント。
青茶や黒茶に向いているのは素焼きの茶器。素焼きの器は香り移りがしやすいので、本来は茶葉ごとに専用茶器を用意するそうです。
香りは聞香杯と言う茶器を使って楽しみます。
白茶や黄茶、紅茶など、香りの高いお茶は、素焼きよりも香りを吸収しにくい磁器を使用するのが良いでしょう。
器に残った香りを楽しめます。
白茶や黄茶、花茶など、茶葉の形や動きを楽しむ茶葉はガラス製の茶器がいいでしょう。
『聞香杯とは?聞香杯について』
聞香杯(もんこうはい)は、お茶の香りを楽しむための細長い茶器です。
台湾で開発され、主に烏龍茶などの青茶に使われます
・聞香杯の使い方
まず、工夫茶器で淹れたお茶を聞香杯に注ぎます。
次にお茶を飲むための茶杯(品茗杯)に注ぎ移します。
空になった聞香杯に残った香りを鑑賞します。
香りをより楽しむために、以下の方法もあります。
品茗杯を逆さにして聞香杯にかぶせます。
聞香杯を挟んで持ち、素早くひっくり返して品茗杯に茶を移します。
聞香杯に残った香りをゆっくりと楽しみます。
聞香杯は、お茶の香りをより豊かに感じさせてくれる道具です。
『重要なのは湯の温度』
中国茶をおいしく淹れるために重要なのは、湯の温度。湯の温度が合わないと、味も変わってしまいます。基本は発酵していないものは低い温度、発酵の進んでいるものは高い温度で淹れるというもの。
六大分類※1でいえば、緑茶・白茶・黄茶は
75〜85度
青茶は85~95度
黒茶・紅茶が100度を目安にしてと言われています。
中国茶の種類によってお湯の温度は異なり、一般的に発酵が進んでいない茶葉は低温で、発酵が進んでいる茶葉は高温で淹れます。
中国茶をおいしく淹れるためのポイントは以下のとおりです
・お湯の温度
緑茶、白茶、黄茶は75~85度。
青茶(烏龍茶)は85度以上の熱湯。95°C~100°Cが目安。
黒茶・紅茶は熱湯。90°C~95°Cが目安。
ジャスミン茶は、香りを立てたい場合は90℃以上の熱湯で、甘みを味わいたい場合には80℃-90℃のお湯で淹れる。
・茶葉の量
100ccあたり2gの茶葉が目安。
150〜200ccの茶器に対し3〜5gの茶葉。
・抽出時間
最初は10秒~30秒で、2煎目、3煎目となるにつれて蒸らし時間を20秒づつ長くする。
・その他
お茶の風味は、お湯の温度、茶葉の量、抽出時間の3つの要素に大きく影響されます。
一般的に、香りを楽しみたい場合は温度を高く、甘みを楽しみたい場合は温度を低くすると良いでしょう。
2煎目以降は、70℃-80℃くらいの温度の低いお湯で淹れると渋味が出にくく美味しくいただけます。
中国茶は、茶葉を洗うことでより香りを引き出すことができます。
軟水を使用すると、お茶の風味が十分に抽出されます。
決まったルールがないだけに、細かいところは十人十色。淹れ方を覚えて、中国茶の味の深さを楽しんでみましょう。
※1 中国茶六大分類について
発酵度による分類で、左から右に行くにつれ発酵度合いの強いイメージです
緑茶→白茶→黄茶→青茶→紅茶→黒茶
黒茶は、微生物による発酵となります。
・緑茶(不発酵茶)
生産量・消費ともにもっとも多いお茶です。ほぼすべて釜炒りでつくられ、茶葉は緑色をしています。
【代表銘柄】龍井茶(ロンジンチャ)、碧螺春(ピロチュン)、緑牡丹(リョクボタン)、黄山毛峰(コウザンモウホウ)
【例えられる香り】豆、草
・白茶(弱発酵茶)
茶葉が芽吹いて白毛の取れないうちに採取し、発酵度が非常に浅い段階で自然乾燥させたお茶です。福建省で多く生産されます。
【代表銘柄】銀針白毫(ギンシンハクゴウ)、白牡丹(パイムータン)
【例えられる香り】くだもの
・黄茶(弱後発酵茶)
荒茶製造工程中に軽度の発酵を行ったお茶です。
【代表銘柄】君山銀針(クンザンギンシン)、蒙頂黄芽(モウチョウコウガ)
【例えられる香り】君山銀針(クンザンギンシン)、蒙頂黄芽(モウチョウコウガ)
・青茶(半発酵茶)
烏龍茶に代表されるお茶です。発酵部分の褐色と不発酵部分の緑色が混じり合って、見た目が青っぽく見えることからこう呼ばれます。大陸産と台湾産があります。
【代表銘柄】大紅袍(ダイコウホウ)、凍頂烏龍(トウチョウウーロン)、文山包種(ブンザンホウシュ)、鉄観音(テツカンノン)、武夷岩茶(ブイガンチャ)、黄金桂(オウゴンケイ)、水仙(スイセン)、色種(シキシュ)
【例えられる香り】花、草、くだもの、実、木、薬、乳
紅茶(発酵茶)
イギリスの紅茶文化を受け、中国で独自に発展したお茶です。代表的な「祁門」は世界三大紅茶のひとつ。緑茶に次いで2番目に多い生産量を誇ります。
【代表銘柄】祁門(キーモン)、正山小種(ラプサンスーチョン)
【例えられる香り】くだもの、花
・黒茶(後発酵茶)
完成した茶葉に微生物を植え付け、発酵させたお茶です。長期保存ができる特徴があり、年代物には高い価値が付けられ、ヴィンテージワインのように楽しまれています。
【代表銘柄】普洱茶(プーアールチャ)、六堡茶(ロッポチャ)
【例えられる香り】薬、木
特別な加工による分類
・茶外茶
【代表銘柄】
ジャスミン茶
茶葉とジャスミンの花を何層にも堆積させ、香り付けを行ったお茶です。
ジャスミン茶
最後までお読みいただきありがとうございます!

今年の夏は『冷泡茶』
冷泡茶とは?
冷泡茶(レンバウチャ)水出し冷茶のことです。
水出し冷茶のことです。
基本的に、すべての茶葉は冷水で抽出することができるのですが、包種茶や烏龍茶など低発酵度茶の冷茶が多い。
茶葉・ティーバックをボトルに入れて、室温で1〜2時間、冷蔵庫で6時間〜8時間置くと出来上がります。
低温の為、タンニン酸やカフェインなどの成分が抑えられ、胃に優しく健康にも美容にもGODD!
苦味と渋みも少なく、すっきりとした甘みのあるお茶に仕上がります。
夏にお湯を沸かす手間なく淹れ方も簡単なので良いですね!
冷泡茶を美味しくお飲みいただくコツは、良い茶葉を選ばないとお茶本来の味わいや香りが無くリラックスタイムが台無しになってしまいます。
良い茶葉を選んで夏の暑さから解放されるティータイムをお楽しみ下さい。
『冷泡茶におすすめの茶葉』
◼️黄金桂茶
【お茶紹介】
諸説色々な話が有りますが黄金桂に関してはキンモクセイ(桂花)の香りと例えられる事が多くその名もキンモクセイ(桂花)と取ったと言われています。
ですが本当に良い黄金桂に関しては“蘭“の花の香りの方が的確なイメージかと思われます
中国福建省安渓産は量がごくわずかということで希少価値が高いお茶として知られています。
芳子のお茶本舗では中国福建省安渓県生産を取り扱っています。
taste : 飲んだ瞬間から華やかさが口の中全体に広がり吐息すらも甘く感じる
aroma : 茶葉もお茶もかすかな蘭の香り
メルカリから黄金桂購入できます!
コチラ↓をタップすると商品情報へ移動します